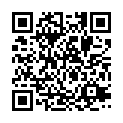会社概要
*伝統工芸士とは
(財)伝統的工芸品産業振興協会では、経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に従事されている技術者のなかから、高度の技術・技法を保持する方を「伝統工芸士」として認定�している。
事業所名:有限会社小川顕三陶房
所在地 :滋賀県甲賀市信楽町長野755−1
代表者名:代表取締役 小川記一
創業:1992年5月
設立:1992年5月
事業概要
陶食器製造販売(販路:卸売業者、小売業者、ゲストハウスでの直接販売)
陶芸体験(しがらき顕三陶芸倶楽部での陶芸体験)
人員体制
陶芸家2名、事務1名(合計3名体制)
(陶芸家:信楽焼 伝統工芸士 小川顕三 小川記一)
沿 革
〇1960年代〜1970年代
1960年、京都の工芸指導所で基礎的な技術を習得した創業者小川顕三は、父である信楽・菱三陶園三代目小川青峰のもとで陶工となる。
家祖伝来の技法と古代の穴窯で桃山・室町時代の茶陶の再表現に取り組んだ父青峰から「古信楽焼の伝統」を学ぶ。
その後、小川顕三は陶芸家として、美と食の巨人とよばれる陶芸家「北大路魯山人」に影響を受け、懐石食器に取り組みはじめる。
併せて1973年からは食器を作り始める。懐石食器をベースに、「信楽らしさ」と「使いやすさ」を両立させた和食器づくりを模索しはじめる。
〇1980年代〜1990年代初頭
小川顕三は本格的な和食器を作るために、御庭焼師の塗師淡斉氏に「つくること」を、京都の高級料亭「辻留」の辻嘉一氏に「料理の盛りつけと器の見立て」を教わる。
また、信楽焼らしさを残した和食器をつくるために、「よごれやすい、水がにじむ」という焼き締め陶器の弱点を釉薬の工夫で克服するために、釉薬の第一人者の大西政太郎氏(京都市工業試験場)に教わる。
そして、信楽の渋さと京焼の柔らかさを取り込んだ“独自の和食器の作風「京信焼」”を確立する。
〇有限会社小川顕三陶房の創業・設立
1992年 小川顕三(55歳)、菱三陶園を退社
1993年 小川顕三が有限会社小川顕三陶房を設立
1992年、信楽が一望できる小高い丘に陶房を構える。
1993年9月、顕三の息子の記一が(株)菱三陶園を退職し 小川顕三陶房に入社する。
同年、陶房の上にギャラリー、宿泊施設等を兼ね備えたゲストハウスを完備した「しがらき顕三陶房倶楽部」を立ち上げる。。
〇しがらき顕三陶房の確立(1993年〜2005年)
この時期、小川顕三は陶芸作家として、東京を初め、仙台、四国で個展を行う。
小川顕三の作る「信楽の土味と京焼の柔らかさを取り込んだ“独自の作風の懐石食器”」は、人気を集め、各地の料亭から大量注文が相次ぐ。
また、1990年以降の陶芸ブームと同時期に開設された「しがらき顕三陶芸倶楽部」もマスコミ等に注目を集め、新聞、トラベル雑誌・ライフデザイン系雑誌等に相次いで掲載される。
〇2005年〜現在
2006年、二代目小川記一が創業者で父である小川顕三の後を継ぎ、代表取締役に就任する。それとともに顕三は相談役となる。
作家としての二代目小川記一は、2006年から現在まで、京都における個展を継続的に開催し、創業者・顕三の教えをベースに、新しい作風の焼き物を創造する。
小川顕三は2006年に、小川記一は2013年に伝統工芸士に認定される。
2014年 小川顕三陶房が甲賀市ブランドに認定される

リンク集はこちら
➡
© 2023 by Dawkins & Dodger Architecture. Proudly created with Wix.com
有限会社小川顕三陶房
しがらき顕三陶芸倶楽部
〒529-1851滋賀県甲賀市信楽町長野755-1
TEL:0748-82-2216
FAX:0748-82-2262
営業時間 10:00~17:00
不定休